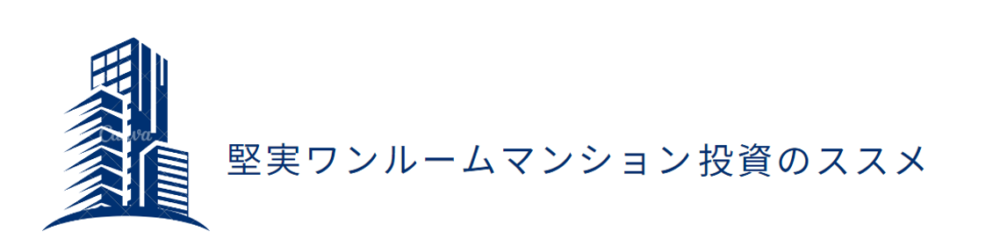不動産投資に興味があるけど踏み出せないという方は、こういう不安があるのではないでしょうか?

不動産投資にはどんなリスクがある?
何に気をつければ失敗しない?
誰しもできれば失敗したくないですよね。
なるべく手堅くやりたいという気持ち、よく分かります。
そこで、今日は、これまで30件以上の中古の区分ワンルームマンションを買ってきた私が考える、不動産投資のリスク13個と、リスクを回避するための方法をお伝えします。
- 不動産投資のリスクの種類
- 不動産投資のリスクを回避する方法
不動産投資のリスクと回避方法
私が考える、不動産投資のリスクは以下の13個です。
- 家賃滞納リスク
- 漏水リスク
- 孤独死リスク
- 金利上昇リスク
- 税金リスク
- 地震リスク
- 水災リスク
- 空室リスク
- 供給過多リスク
- 価格下落リスク
- 修繕積立金の値上がりリスク
- 買ってみたら中ぼろぼろリスク
- 退去したら家賃大幅下落リスク
※ 初心者の頃から変わらず「中古区分マンション」をメインに持っており、「中古区分マンション」を前提にしています。
私がなぜ「中古区分マンション」をオススメしているのかは、下の記事をご参照ください。
以下、不動産投資のリスク詳細と回避策を順にお伝えします。
数が多いので、この記事では1〜7のリスクについて書きます。
▼(後半)8〜13のリスクは下の記事をご覧ください。
不動産投資のリスク13個と失敗を防ぐ方法(後半)
不動産投資のリスク1:家賃滞納
自分が所有する物件を貸している相手(=入居者)が家賃を滞納することで、オーナーである自分に家賃収入が入ってこなくなるリスクのこと
少し前のデータですが、2018年下期の家賃を滞納する人の割合は下記のとおりです。
月末での1ヶ月滞納率
全国で2.6%、首都圏で2.3%月末での2ヶ月以上滞納率
出典:日本賃貸住宅管理協会『第21回 賃貸住宅市場景況感調査』
全国で1.4%、首都圏で1.1%
このデータによれば、全国40戸に1戸は1ヶ月滞納が発生し、70戸に1戸は2ヶ月滞納が発生しているようです。
自分の物件で家賃滞納が起こるリスクはある、と思っておいたほうがいいですね。
対応策は以下です。
- 物件を買う前に、※家賃保証会社をつけているか、オーナーが変わっても保証会社を引き継げるかを不動産会社に確認する
- 保証会社をつけていないor引き継げない場合は、購入後に自分で保証会社をつける
- 物件を買う前に、これまで滞納がないかを売主に確認する(嘘をつかれることもあるので参考程度)
- 入居者に支払い督促をしてくれる、きちんとした管理会社(オーナーの代わりに部屋を管理してくれる業者。マンション全体の管理会社とは別)をつける
※家賃保証会社とは、連帯保証人の代わりのように、入居者が家賃滞納時にはオーナーへ家賃を支払ってくれます。家賃保証会社が入居者への回収します。滞納が続くと、強制退去の手続きをしれくれます。
私自身、家賃保証会社がついてない物件を購入し、保証会社をつけた後に入居者が家賃を滞納した、ということがありました。
家賃保証会社をつけることを強くオススメします。

不動産投資のリスク2:漏水
物件の入居者が漏水を起こすことで、他の部屋(主に下階の部屋)の修繕が必要になるリスクのこと
漏水は、お風呂の水の止め忘れや、洗濯機の水栓の閉め忘れが原因で水が溢れて起こります。
下階の部屋の天井や壁紙、家具・家電などに被害が及ぶので、修繕費用が大きいです。
対応策は以下です。
- 火災保険に追加して「施設賠償責任保険」に入る
(保険会社によって名前が違う場合があります。)
不動産投資のリスク3:孤独死
物件の入居者が孤独死して発見が遅れた場合に、物件が損傷するリスクのこと
亡くなった入居者に身内がいない、あるいは、身内がいても費用を支払ってもらえない場合には、オーナーが物件のクリーニング代や修繕費用を負担することになります。
また、程度によっては事故物件扱いとなり、家賃を大幅に値下げせざるを得なくなることもあります。
ワンルーム物件は基本的に単身入居なので、特に注意が必要です。
対応策は以下です。
- 火災保険に追加して「家主費用特約保険」に入る
(保険会社によって名前が違う場合があります。)
部屋で亡くなるのはシニア層とは限らないので、入居者の年齢にかかわらず加入されることをオススメします。

不動産投資のリスク4:金利上昇
物件購入のために銀行からお金を借りた場合に、利子が上がって返済額が増えるリスクのこと
2020年4月現在は超低金利時代のため、今後は金利が上がる可能性のほうが高いです。
変動金利でしか借りられない銀行が多いですが、可能な場合は固定金利で借りることをオススメします。
対応策は以下です。
- 固定金利で借りられるなら固定金利で借りる(日本政策金融公庫など)
不動産投資のリスク5:税金
本業の給与に不動産投資の収入が加わることで、支払うべき税金が増えるリスクのこと
所得が増えれば税金も増える、ということを忘れないようにしましょう。
対応策は以下です。
- 本業の給与があるうちは物件購入を継続して支出(経費)を増やし、税金の大幅増加を防ぐ
- 法人化を検討する(不動産投資を始めてからでOK)
物件を買うと、どうしても不動産取得税や登記費用で経費が発生します。必要な経費で所得が減るので税金を少なくすることができます。

ただし、割高な物件は買わないように!
私もサラリーマンとしての所得がそれなりにあり、不動産投資の収入が加わると税金がかなり高くなってしまうので、不動産投資を始めて2年目で法人をつくりました。
今ではほとんどの物件を法人名義で購入しています。

不動産投資のリスク6:地震
地震によって物件が損壊、倒壊するリスクのこと
対応策は以下です。
- ハザードマップを見るなどして、地盤の強い地域を選ぶ
- 液状化地域は避ける(風評被害が起こりやすい観点でも避けるのがベター)
他にも、新耐震基準(1981年6月〜)で建てられた物件を選びましょうと書いているサイトが多く、私も同意です。
ただし、地震に強いからというより、銀行の融資条件に新耐震が入っているため、新耐震基準の物件しか買いません。
また、地震保険の加入をすすめるサイトも多いですが、この点には私は懐疑的です。
理由は以下。
- 地震保険では損害の程度が4段階に決められており、新耐震マンションの大多数は一部損で5%の額しかもらえず、支払う保険料とリターンが合わない
- 区分マンションでは、保険で自分の物件(一部屋)を直せたところで、マンション全体や共用部分が直されなければ意味がない
- 保険金がたくさんでるような状況では東京が壊滅的で保険金の請求どころではない
- ちきりんさんも同様のことを言っている→マンションの地震保険とか意味不明
不動産投資のリスク7:水災
大雨や川の氾濫などの水災によって物件が損壊、倒壊するリスクのこと
近年は異常気象で大雨が降ることも増えました。
地震災害より存在感が小さいですが、水害も見落とせません。
対応策は以下です。
- ハザードマップを見るなどして、低地や川の近くなどリスクの高そうな地域を避ける
- 1階の物件は避ける
- 火災保険で水災にも加入をする

不動産投資のリスク8〜13
▼ 続き(後半)は下の記事をご覧ください。
下記8〜13のリスクについて書いています。
- 家賃滞納リスク
- 漏水リスク
- 孤独死リスク
- 金利上昇リスク
- 税金リスク
- 地震リスク
- 水災リスク
- 空室リスク
- 供給過多リスク
- 価格下落リスク
- 修繕積立金の値上がりリスク
- 買ってみたら中ぼろぼろリスク
- 退去したら家賃大幅下落リスク

リスクを事前に知っていて対策すれば安心ですね。
今回は以上です!それではまた!
堅実リーマン
最新記事 by 堅実リーマン (全て見る)
- 不動産投資の勉強方法を解説!【99%の初心者がしていない最強の方法】 - 2022/11/03(木)
- 不動産投資で最初に買った物件は?体験談と失敗の考え方 - 2022/10/30(日)
- 中古ワンルームマンション投資は儲かる!【所有物件すべて収支公開】 - 2022/10/27(木)